
(画像は20世紀フォックスDVD販売サイトより)
映画『ナイトメア・アリー』を見ました。ウィリアム・リンゼイ・グレシャムの小説『ナイトメア・アリー 悪夢小路』を原作とし、ギレルモ・デル・トロ監督が映画化した作品です。
***
主人公はスタン。見世物小屋に拾われ、読心術の出し物をしていたところ、座員・モリーと恋仲になり、一団を抜け出して独立することになります。高級ホテルで降霊術のマジックを披露していたスタンは、戦争で息子をなくしたキンブル判事夫妻と出会い、話術とちょっとした手口(是非映画で見てください)で、夫妻に亡くなった息子がそこにいて、また会えるかのような体験をさせます。
ところが当然、実体として息子はいるわけはないので、息子に合うには死ねばよいのだ(死ぬよりない)と思い込んだキンブル夫人は、夫を撃ち、自分にも銃を向けます。さらに、女性を妊娠中絶させ死に追いやった経験のある大富豪・グリンドル氏にも、その助成と会うことができると持ちかけ、多額の金を得ます。モリーに変装させ亡くなった女性がそこにいるかのように演出しようとするのですが、グリンドル氏に見抜かれ、逆上した氏にスタンは殺されそうになります。反撃してグリンドル氏と用心棒を殺めたスタンは逃亡を余儀なくされます。そしてある見世物小屋にたどり着いたところで、生きた鶏をむさぼり食う出し物としての獣人(ギーク)となることを選び取ったのでした。
こうしてあらすじを抜き出すと味気なくなりますが、美しい装置と映像によって夢のような世界に優しく導かれ、気がつけば巡りくる因果に囚われるしかなかったゴールでストンと現実に引き戻される体験は、映画を見なくては味わえないものだと思います。
***
この映画から導き出される一番の教訓(?)は、亡霊は亡霊でないといけないということだろうと思います。つまり、亡くなってこの世ならぬ存在になったものは、しっかりとあちらに送り出さないといけない。そして安全な方法で、安全なときにそのイメージだけが取り出されなければならない。
臨床心理学や精神医学の世界では、こういった「あちらに送り出す」プロセスを「喪の作業」と呼びます。これを概念化したのはフロイトで、悲哀と思慕を感じながら、最終的には対象への執着を断ち切り克服しなくてはならないと考えました。現代では、ただ断念するのではなく、「継続する絆(continuing bond)」と言って、形や次元を変えて故人とのつながりを保っていくことが、生者が生者としてこの世にあるために大切なのだと考えられるようになりました。つまり、あちらとこちらを分けつつつなぐのが本来の喪の作業であり、心理療法の一つの役割として、このプロセスに立ち会うこともあります。
故人を思う思慕の念は、生死と直結するものですから、安易に扱えばそれは畢竟、誰かの死につながります。人が人を思う心はそれほど強い力を持つものです。そういった念を閉じ込めている扉は、用もなく欲のために開いてはいけないのです。これは、心理士としての自戒の意味でも触れておかなくてはならないことです。
***
その一方で、スタンの人生を考えると、また、映画は一つのフィクションであり比喩でもあると捉えると、バッドエンドのように見えるギークとしてのスタンの誕生も、違った見え方をするものです。実はスタンは見世物小屋を出る前に、読心術を自分に教えたピートに密造酒を出し、それによってピートは亡くなっています。人を死に追いやった自分にも、有能な人間でいることで存在価値があるのだと思い込もうとしているように見えますし、父親のような手本としてのピートを追いかけることで、代償しようとしているようにも見えます。これは罪悪感からそのようにしているようにも見えるかもしれませんが、罪悪感が自分の卑小さを受け入れることから始まるのだとすると、こういったスタンの行動は、罪ある存在である(誰しも多かれ少なかれそうであるような)自分を受け入れることからの逃避であると言えます。
アディクションのことでもよく言われることですが、いつかは破綻する追いかけっこのような逃避の日々は、破綻することが一つの安堵となり、それがゴールではなくスタートにもなりうるようなものです。つまり、自分を含めた誰かを傷つけた血に塗れた存在として生きることを受け入れることから真の罪悪感が生まれるのだと考えると、心理的に獣人として丸裸になったスタンの誕生に立ち会うことが心理療法であるとも言えるのだと思います。(そう思うと「エノク」の存在―これも映画でご確認くださいーもよくできていると思います。)そういった意味で、心理療法の真価について考えさせられる興味深い映画であったと思いました。

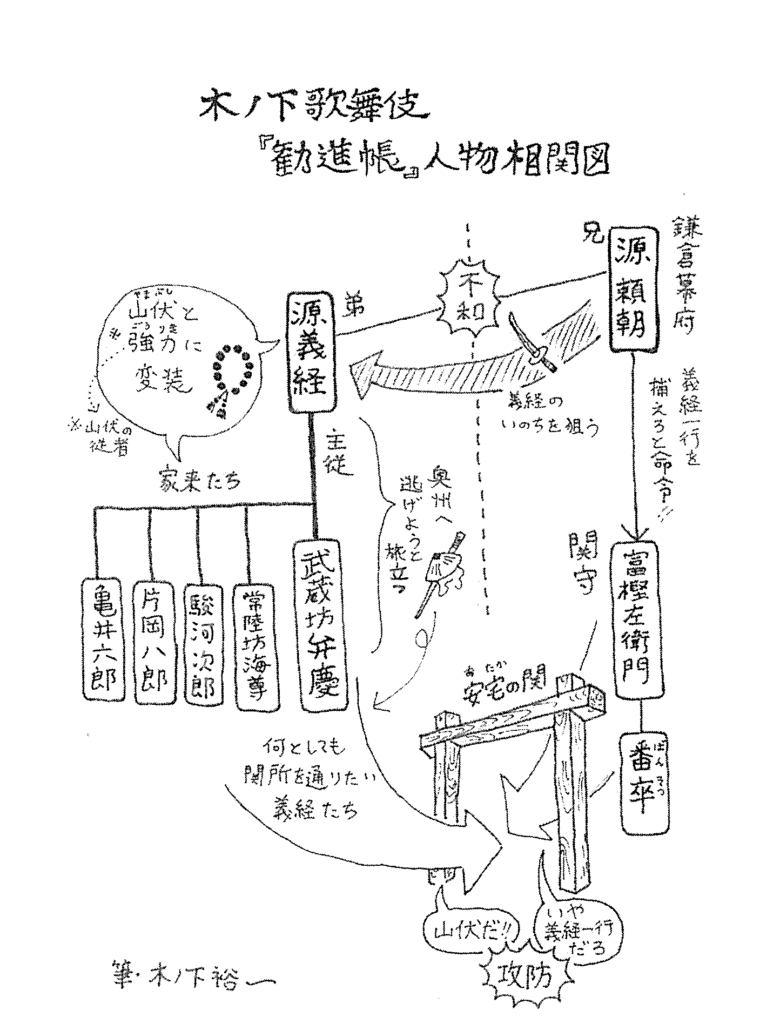


 この図は
この図は



